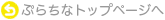2000年以降、日本のアニメ制作環境は、大きくデジタル化へと舵をきりました。その流れの中で、3DCGによる表現とセルアニメの融合が進んだことは、この10年アニメが迎えた変化の中でも、かなり大きなものだといえるでしょう。「アニメのゆくえ2011→」第2回は、『TIGER&BUNNY』や『輪るピングドラム』など、今まさに話題の作品の3DCGを手がけ、大きな存在感をみせているアニメーション制作会社、株式会社サンジゲンの松浦裕暁さんへのインタビューを通じて、アニメにおける3DCG表現のこれまでとこれから、次の10年に3DCGがアニメにもたらすものは何かを探ります。GO→NEXT!
⇒特集第1回 アニメ評論家藤津亮太氏インタビューはこちら
⇒特集第3回 ニトロプラスでじたろう氏インタビュー
⇒特集第4回 ウルトラスーパーピクチャーズ
3DCGで「日本のアニメ」を目指す

――松浦さんがアニメ業界に入られたのはいつ頃なのでしょう?
松浦 1998年です。25歳のときですね。(制作の)デジタル化が始まったばかりの頃でした。デジタル制作はまだまだだ、やはりすべて手描きで作る方がいいんじゃないか……というような議論が、まだ熱心にされていたころでしたね。
――ほとんど制作工程がデジタル化した現在から考えると、隔世の感がある議論ですね。
松浦 もともと僕はそこまで熱心なアニメファンではなかったので、当時も議論する意味がよくわからなかったんですよ(笑)。別にどっちでもいいじゃないか、アニメを作るために必要なことはほかにもたくさんあるのに、どうして技術のことだけを重要だと考えるんだろう……と思っていました。
――当時かかわられていたのはどういったタイトルだったのでしょう?
松浦 当時はフリーで、ミルキーカートゥーンという会社の『ペコラ』という、子供向けの内容のフルCGアニメに関わっていました。カナダのネルバナ社との共同製作で、海外から送られてきたCGモデルに、日本のスタッフがアニメの芝居をつけるという、ピクサーのような作り方のアニメでしたね。それはそれで効率の良い作り方で、作るのが嫌だということもなかったのですが、「このやり方では海外と勝負できない」という思いがあったんです。
――海外の3DCGアニメと対抗するのに、同じ方法論でやっていてはダメだ、と。そこから今のサンジゲンへと繋がる、作画と3DCGの融合という作り方を考え始めたのはどういったきっかけで?
松浦 『ペコラ』のあとにGONZOに入って、『ヴァンドレッド the second stage』で初めてCGディレクターを任されたときに、作画と3DCGを融合させることを意識し始めました。当時は作画とCGは全く別のラインで動いていて、画をすり合わせることがほとんどなかったんです。GONZOには第1作の『青の6号』以来「一発でレンダリングする」というポリシーがあって、「3DCGを合成する」という文化がなかったんですね。でも戦争シーンの多い作品で、爆発も多いのに、それをいちいちレンダリングしていたら制作が終わるはずがない。だから実写映像を合成して爆発のエフェクトをつけたりする作り方を始めたんです。そのほかのところも、合成も使うことを前提にして作ろうと思いました。
――爆発以外のところだと例えば?
松浦 背景に宇宙を描くとき、一作目の『ヴァンドレッド』では、3DCGで描いていたんです。『ヴァンドレッド the second stage』では、大きなテクスチャで背景を作って、それを3DCGと合成するようにしました。その結果、生産性とクオリティコントロールを両立できるようになったと思いますね。一発でレンダリングするやり方は、たしかにGONZOが立ち上がってすぐのころは画期的でしたし、出来上がった画面も斬新なものだったと思います。ただ自分の見た限りでは、当時の技術的に仕方がない部分もあったにせよ、斬新な「だけ」だったんです。
――新しくはあるけど、面白くはなかった、というところでしょうか?
松浦 それ以前に、とにかくCGと作画を合わせたときの違和感がひどかったように思いますね。CGにはテクスチャーを貼ってディテールが入れられるけれど、作画されたものにディティールを入れるには描きこみを増やさなければいけない。(TVアニメーションの制作スケジュールを考えると)どうしても、作画にはCGほどのディティールが入れられないんですよね。

――同じ画面で並んでいるのに、CGで描かれたものと作画されたもののあいだで情報量に差ができてしまうということですね。
松浦 そのギャップがすごかったんですよ。実写映画にアニメのキャラクターが登場する映画がありますよね。あれも発想は面白いですけど、やはり観ていて違和感がありませんか? 僕はそうした違和感があると、お客さんはシラけるんじゃないかと思うんです。感情移入していたところに、別の質感、別の次元のものが入ってくると醒めてしまうのではないか、と。
――たしかに、わかります。
松浦 『サマーウォーズ』のように、電脳世界のシーンだからCGの質感を見せます、というかたちで、演出として上手くいっている場合は、違和感があってもいいんですけどね。同じ空間、同じ世界の中で、ドアを開けたら別の質感というのは明らかにおかしい。僕はそういう風に感じていました。
――つまりそれは3DCGのクオリティが高くなれば解消される問題でもないですよね。
松浦 そうですね。また、ちょうどその頃、ゲームのCGムービーが盛り上がっていたんですね。『アーマードコア』のムービーとか、カッコいいとは思っていたんですが、あれは日本で普通に作られているアニメの延長にはないな、と感じていたんです。それは映画の『ファイナルファンタジー』も同じで、どちらも「ゲームのムービー」であって、「日本のアニメ」ではない。だから質感の違いによって生まれる違和感の問題をクリアできるほどのポテンシャルは持っていないと思っていました。
――松浦さんとしては「日本のアニメ」であることにこだわりたいという思いがあるんですか?
松浦 やっぱり、日本で暮らす僕らが子供のころから刷り込まれているのは「日本のアニメ」なんですよね。さっき、「自分は熱心なアニメファンではなかった」といいましたけど、それでもやはりそういう感覚はあるんです。また、ジブリや『新世紀エヴァンゲリオン』の人気を思えば、そこに大きなマーケットがあるのは明らかで、そこに向けて作った方が効率的だと思ったんですね。ピクサーを目指しても、現時点では日本のアニメファンのニーズとはズレますし、海外市場を考えたときにも、同じ土俵に立って取っ組み合いをしなければならないから、戦略的にダメだと考えました。
かたや1000人以上の社員がいて、数十億の予算をかけて作られるものに対して、日本のCGアニメは多くても10億円から15億円くらいしか予算を使えない。仮に予算をかけたとしても、日本の国内市場だけでは制作費を回収できない。それなら今ある市場に向けて作ればいい。そう考えたときに、色々なことが見えてきたんですね。
――たとえば?
松浦 まず気付いたのは、3DCGの質感を、CGならではのグラデーションがかかっているようなものではなく、塗り分けにすることですね。そうすることで、まず制作費が下げられて、通常の劇場用アニメの予算で、3DCGの劇場用アニメを制作することができるようになる。質感を変えても内容は自由ですから、企画次第で日本のマーケットに乗せることができる。
そしてもうひとつ、「日本のアニメ」を目指せば、歴史をかけて作られたリファレンス(参考資料)が山ほどあることに気付いたんですね。そうしたことを考えたとき、僕らの目指すものは「日本のアニメ」なんだ、とすごくハッキリしてきたんです。
――なるほど! そうした考えをもとに、サンジゲンを立ち上げられた。
松浦 そうです。アニメにCGを使うためには、常に自分で考えて、新しいことをやっていかないと、技術的に乗り遅れてしまう。会社員として働いているとなかなかお金も行動も自由にできない、かといって個人でやることにも限界はある。それなら、自分自身で、ある程度自由に技術に投資できる環境を作ろう……そう考えて、会社を立ち上げることにしたんです。