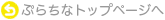■伊藤剛のパリ・マンガレポート

「マンガは日本を代表する文化」とはよく耳にしますが、実際に世界ではマンガがどのように受け入れられているのか? 日本を代表するマンガ評論家のひとりとしてフランス・パリで開催されたマンガ研究国際会議に招かれた、アミューズメントメディア総合学院マンガ学科講師の伊藤剛先生に、国際会議とパリ・ブックフェアの様子をレポートしていただきました。現地からみた、日本のマンガ、世界のマンガのこれから――
この3月、パリで開催されたマンガ研究国際会議「マンガ、60年を経て……」に招かれ、発表とディスカッションに参加した。この会議の主催者であるパリ政治学院のジャン・マリ・ブイス氏をはじめ、フランス、ベルギー、ドイツ、スイス、イタリア、オーストラリア、そして日本の研究者たちが一同に会したものだ。その様子などを簡単に報告したいと思う。
日本の「マンガ」が、世界の各地で若い人々に受け入れられ、人気を得ていることは、すでによく知られているだろう。また、大学などでマンガを学問的に「研究」する営みが進められてきていることも、それなりに知られている。今回のような国際会議が開かれるということは、そうした「マンガ」を取り囲む変化を、よくわかる形で見せてくれる。この会議は、ヨーロッパにおけるマンガ研究者のネットワーク、“MANGA NETWORK”の企画で、毎年開かれている。そして「マンガ・ネットワーク」の「マンガ」とは、主に日本のマンガのことを指している。
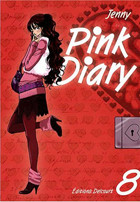
フランス人作家が描いた「マンガ」Jenny作『Pink Diary』
作者はマダガスカル移民のフランス人女性。作品の舞台は東京、女子高生が主人公のラブコメディだ。すでにフランス語版は既刊8巻を数え、ドイツ語版も出版されている。日本語版も出版の予定。
ご存じのとおり、フランスをはじめ、ヨーロッパの各国でも、日本マンガやアニメのファンは増えている。近年はもう少し進んで、日本マンガやアニメを喜んで消費するというだけでなく、日本スタイルの「マンガ」を描く若いひとも現れ、出版もはじめられている1)。私も、会議の間のオフの日(驚くべきことに、短期間の会議でも日曜はきっちり休む)、ちょうど開催されていたブックフェアに行き、「少年ジャンプ」系の作品を中心に、翻訳出版をする会社のブースがいくつも出展されて盛況を呼んでいる様子を目の当たりにしてきた2)。フェアでは、楽しいアトラクションとしてファン有志によるコスプレ・ショウも行われ、日本アニメやマンガのファンが、すっかり定着している雰囲気が感じられた。”MANGA NETWORK”の活動がはじめられたのも、こうした社会の変化に対応してのことだろう。じっさい、二日目のセッションでは、日本マンガの翻訳出版をしている会社や、翻訳の実務に携わっているひとの発表も行われた。

パリのブックフェアの様子……出版社がブースを出し、書籍などを展示・販売するイベント。日本ではあまりなじみがないが、ヨーロッパではこうしたフェアも一般読者の楽しみになっている。パリのブックフェアはなかでも最大級の規模のもの。
さて、マンガ研究、それも大学などで行われる学術的なそれというと、普通にマンガを読んでいるひとからは、ひどく縁遠い話題に思われるかもしれない。「マンガは誰にでも分かりやすく、親しみやすいものだから、ことさらに難しく考えるのはおかしい」というひともいるかもしれない。
だが、意外にそうでもない。私はアミューズメントメディア総合学院や、東京工芸大学のマンガ学科でマンガの、主に「コマわり」の仕方を教えている。学生の皆さんは、そうした学校でマンガを素朴に楽しんで「読む」立場から、一歩「作り手」の側に踏み込むことになる。そこで、私のような先生の立場にいる者がやっていることは、「研究」といったものにも近くなる。マンガ家の皆さんが感性で体得してきたものを、学校で「教える」となると、とたんにいろいろなことを考えなければならなくなるわけだ。なぜなら、フィーリングで行われてきたものを、いちいち分かりやすい言葉にして、順を追って説明しなければならないからだ。
学校では授業を通して、いろいろなマンガの技術を分析し、できるかぎりわかりやすく教えているのだが、そこで分かってきたことを整理し、もういちど振り返って他のジャンルの表現とのつながりまで考えると、いつのまにか「学術的研究」と呼ばれるものになる。ものすごく大まかにいえば、そんな感じだ。
話をパリでの会議に戻そう。出席した各国の研究者たちは、大きく「日本文化」に関心があり、そのユニークなあらわれとして「マンガ」を扱うというひとと、日本に限らず「マンガ」に関心があり、その独特な発展をしたものとして「日本のマンガ」を扱うひととに分かれるように見えた。そして、もうひとつ、ヨーロッパや他の地域に根づきはじめている「オタク」という現象に関心が向けられていた。
ここで、ちょっと注釈的な説明をしておく必要がある。

『DEATH NOTE』や『NARUTO!』などの翻訳出版をしている会社「KANA」のブース。「KANA」はベルギーのブリュッセルに本社を持ち、『NARUTO!』はフランス語圏ではダントツの約25万部というセールスを誇る。
「マンガ」的な表現―コマがあって、絵と文字とフキダシで語られるもの―は、日本だけのものだと思っているひとがいるけれど、そうではない。アメリカには「アメリカン・コミックス」があるし、フランスを中心としたヨーロッパには、「バンド・デシネ(略称BD)」がある。日本でとくに発展したスタイルのものが、おおむね「Manga」と呼ばれている。「マンガ・ネットワーク」が、わざわざ日本語で「マンガ」と断っているのは、そのためだ。
アメリカン・コミックスも、BDも、それぞれに歴史があり、優れた作品があり、研究も進められている。もし、日本のマンガ<だけ>が特に優れていて、だから外国でも認められたんだ、とか、マンガについての学問的な研究は日本ではじめられた、とか思っている人がいたら、それははっきり間違いだ。世の中には「マンガファン」という大人たちがいて、わりと無邪気にこういうことを言ったり書いたりしている。でも、外国の事情を知らず、知ろうともしないで言われている場合が多いということは、知っておいたほうがいいだろう。
私にとってこの会議は、わずか四日間の滞在とはいえ、多くのマンガ研究者や出版関係者と議論ができる貴重な機会だった。
初日の様子から記していこう。初日・土曜日はセーヌ川のほとり、エッフェル塔のすぐ近くにある日本文化会館3)で「少女マンガ」をめぐるものと、「オタク現象」という二つのセッションが行われた。この施設は日本の国際交流基金が運営している。
Gunslinger Girl

私が参加したのは午後のセッション「Le phénomène otaku オタク現象」。著書『動物化するポストモダン』4)のフランス語訳が出たばかりの東浩紀の発表もあるこのセッションはたいへん人気で、百席ほどの客席は満席、あとできいた話では、かなりの人数の入場を断ってしまったのだそうだ。
この日のセッションでの議論でのちょっとしたトピックは、オーストラリアの研究者、クリスティ・バーバー氏の発表がアニメ『Gunslinger Girl』(原作・相田裕)をめぐる考察だったことだろう。『犠牲となったサイボーグ 『GUNSLINGER GIRL』の断片的自己表象』と題した、同作のヒロインのあり方についての論考の予報のようなものだったが、これには軽く驚いた。なぜなら、私の発表でも、別の切り口からとはいえ、マンガ原作版の『Gunslinger Girl』を取り上げていたからだ。そして少しの間だけれど、この作品の解釈について軽く議論にもなった(さらに帰国後、この会議で議論になったということを東氏のブログで知った某大学の社会学研究室が『Gunslinger Girl』の単行本をまとめて購入したという話もきいた。念のため明記しておくが、パリでの発表も議論も、この作品を否定的に捉えるものではなかった)。

さて、主催者側から私に与えられた論題は “Did the OTAKU generation drive TEZUKA to grave? “ 『オタク世代はテヅカを墓に葬り去ったのか?』。おそらく私の主著である『テヅカ・イズ・デッド』というタイトルから発想されたであろうこの問いに、私は「それは “ウイ”でもあるし、同時に”ノン”でもある」と答えることからはじめた。「もし手塚治虫が『映画的』であったがゆえに戦後ストーリーマンガの始祖であるという史観なら、「ウイ」だが、オタクたちの『萌え』などのキャラに関する感性という意味では「ノン」だ。むしろそこにこそ”テヅカ”は生きている」という論旨の発表を行った。詳しくは別ファイルに全文原稿(日本語/pdf形式)をアップしたので、関心のあるひとは読んでほしい。また、東浩紀氏の発表や、このあと月曜日に行われた発表の一部は、批評誌「ユリイカ」(青土社)の2008年6月号に掲載されているので、こちらも興味のあるひとは手にとってみてほしい。
ユリイカ2008年6月号

ところで、「手塚治虫」という名前は、若いひとには「偉いといわれてる昔のマンガ家」というイメージでとらえられているだろう。学校や地域の図書館で読んだことはあるが、「いま」のマンガとはつなげられないものというほどの認識だ。ところが、いま四十代以上のマンガ関係者は、とかく「手塚は知っててあたりまえ。知らないのは若い連中の不勉強」と考えがちで、そのため手塚をはじめとする昔のマンガを、「いま」の読者である若い人たちの興味を惹くかたちで説明することができない。
私が「オタク世代はテヅカを墓に葬ったのか?」というタイトルに、それは「ウイ」でもあり「ノン」でもあると答えたのは、このギャップをどうにかして埋めようという気持ちからだということは、しっかり記しておきたい。これは、私が「マンガを教える」学校の先生を続けていて持っている、もうひとつの問題意識だ。マンガ界の古い常識にとらわれることなく、「いま」の学生さんにとって有益なものをどうすれば提供できるか、ということでもある。だから、授業では意識して「いま」のマンガと、「昔」のマンガの両方を例として見せている。マンガという表現を成り立たせている「基礎」をしっかり分析していて、はじめてこの「両方」をつなげられるのだと思う。

カンファレンスの壇上で発表する伊藤先生。(右隣は東浩紀氏/photo by 中田健太郎)
そういう意味では、このカンファレンスで、ブリュッセル高等美術学院教授のパスカル・ルフェーヴル氏や、パリ第七大学のグザヴィエ・エベール氏ら、フランス語圏で「マンガ」を研究している人々と知り合えたことは、私にとってたいへんな喜びであり、収穫だった。
初老のルフェーヴル氏と、若いエベール氏のコンビは、二日目午後のセッション「文法と話法」で、日本マンガにおける「演出」と「フレーミング」の分析について発表した。そこでは、1947年の『サザエさん』、1953年の手塚治虫『罪と罰』から、1999年の高橋ツトム『地雷震』、2001年のすえのぶけいこ『ビタミン』まで六作品をとりあげ、戦後マンガ史を駆け足でたどるかのようにして、手際よく表現技法について分析を行った。私が驚き、喜んだのは、「マンガ表現論」について、私たちが日本で進めているのと近い方法で、少し違った達成を見ていたからだ。ああ、議論の相手がいた! ちゃんといてくれた! という嬉しさがあった。

会場であるパリ政治学院前。海外の研究者たちと談笑する伊藤先生 (photo by 中田健太郎)
彼らが扱った作品群は、日本のマンガ読みにとっては、「あっち」と「こっち」の作品を適当につまみ食いして論じてみせただけに見えるかもしれない。だがそんなことはなく、マンガにおける基本的な「コマ」の使われ方と「演出」との関係を実に手際よく取り出してみせるものになっていた。彼らの対象を扱う方法論の確かさもさることながら、彼らがフランスやベルギーにいて、日本と距離があったことがよい方向に出たのだと思う。私たちは、とかくマンガに親しみすぎていて、つい近くからものを見てしまう。細かい事実関係や差異に気を取られてしまうのだ。ルフェーヴル+ヘベールの発表も、「ユリイカ」に翻訳が掲載されているので、興味のある人はぜひ読んでほしい。
「マンガ」は、いまや日本人だけのものではなくなった。そして、これからの「マンガ」はもっと変化するに違いない。短い滞在だったが、フランスでの体験は、そんなことを考えさせてくれた。
レポート:伊藤剛(AMGマンガ学科講師)