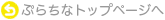[第6回]『虹色ほたる~永遠の夏休み~』アニメーションの輝きが照らす問題
『虹色ほたる』を見た。
とてもみずみずしい映画だった。
物語はいたってシンプルだ。
小学6年生のユウタは1年前に亡くした父の思い出をたどるように、ダムのある山奥へと向かう。不意の豪雨に流されて崖下へ落ちたかと思ったユウタは、夕暮れの草むらの上に寝そべっていた。そこは1977年の夏。ユウタは、ダムに沈んだはずの村のはずれにいたのだ。
ユウタは、不思議な老人に、現在に戻るまでの1ヶ月間を、この村で過ごさなくてはならない、と告げられる。ユウタは、ユウタをいとこと呼ぶさえ子や、同い年の少年ケンゾーたちと、かけがえない時間を過ごすことになる。
郷愁をもって描かれる「夏の田舎の風景」「小学生の夏休み」。言葉にすればずいぶんとありきたりの内容になってしまう。確かにエピソードだけひろえば、本作はさほど特徴的な内容とはいえない。本作の魅力は、その児童文学的なクリシェを、作画と美術の力でみずみずしい映像体験へと昇華している点だ。
とはいえそれは、本作が“作画(と美術)だけ”が見どころの映画ということを意味するわけではない。さえ子の回想シーンなど、演出と作画が絡み合ったシーンこそ、本作の見どころであるのは強調しておきたい。
アニメは、まずなによりも絵である、
ここで「絵である」ということは、言葉にすればシチュエーションを描いたとしても、描かれた絵によって、それはまったく違うものになってしまう、ということでもある。
本作のキャラクターは、描線が太く、ひじなどではところどころ描線が途切れている(アップ時は細めの色トレスが引かれている)という独特のスタイルで描かれている。たとえば指先などは、指の輪郭線がちゃんと閉じていないので、太い絵筆でそのまま絵の具を置いたように色が“はみ出して”いるように見える。リアルというよりは、絵本などのキャラクターに近い印象もある。
ここに印象的な動きが加わる。本作では、登場人物の細かな仕草を拾いつつも、緻密さというよりも、その仕草のおもしろさを大胆に絵にしていく方向で作画が描かれている。
たとえばその作画の方向性は、類似した題材(小学校高学年の夏の暮らしを描く)を扱った『ももへの手紙』と比較すると、一層際だつ。
『ももへの手紙』の作画は「そのキャラクターがあたかも実在するかのようなリアリティ」を求めている。そのため物理的な存在感(量感やものの形状、空間的奥行き)をまず非常に大切にしている。キャラクターが演技をする時も、こうした物理的な条件で規定された「キャラクターという器」は非常に大切に扱われている。
それに対し、本作の目指すリアリティは「クロッキーの持つ生々しさ」といえる。たとえば本作は口パクの形が独特で、上唇の線が非常に生々しく、それが“上あごの形状”を想起させてキャラクターの生々しさにつながっている。
『ももへの手紙』であれば、「実際にこの角度から見たらこう見えるだろう」と論理性と緻密さでアプローチをするはずであろうことを、観察をもとにしつつも、ざっくりとした1本の線に託してしまうのが本作の絵柄=世界観であるといえる。
そのため本作は、時として物理的な「キャラクターの器」を壊してでも、その時の心情を素描しようとする。その筆頭が青天狗と呼ばれる神社の神主とユウタが会話をするシーンだ。ここは本編の中でもかなり「描きだそうとする心情」が「キャラクターの器」からあふれだしてしまっているシーンだ。
このシーンは、演出の狙いを越えて、いささか踏み外している感(絵に意識がとられてしまい、ドラマに意識が向かいにくくなってしまう)もあるのだが、しかし、本作の作画を貫く世界観が一番前面に出ているシーンであるのは間違いない。
現実を観察することからはじまった素朴な表現が、やがて深まり記号化するようになり、さらには記号と記号を掛け合わせた技巧的な高みへと至る。
あらゆる表現はおおむねそのような流れを繰り返している。記号と記号を掛け合わせたメタ記号的な表現は、一方で現実と遊離しているため「記号として消費されること」にはたけるけれど、表現の原初の力は失われてしまっている。
この時、文学ならば、言文一致――口語を小説の言葉に生かすことで、現在の記号でできている世界とは新たに別の世界を切り開くことになる。
アニメであれば、それは現実をもう一度観察するところから初めて、あらたな絵柄を開発することに相当するだろう。絵柄というのがたぶんに属人的であることを考えると、そういう絵を描く人をいかにアニメ業界に取り込むことと考えるということでもあろう。
いうまでもなく現在のアニメの絵柄の記号性はかなり高まっているし、その記号を操作することに対するファンや作り手の感度も高いレベルにある。
メタ記号的な表現の高まりは、それはそれで悪いことではない。だが、それはどんどん狭くなっていく道を歩いていくようなものだ。どこかでなんらかの風穴が必要になるのは間違いないし、「萌え」という言葉が生まれて約20年。TVシリーズの絵のばらつきが底上げされて約15年。そろそろ道は狭くなってきているようだから、もう一度新たなルートを探る変化が必要な時期のようにも思う。
『虹色ほたる』を見ると、今必要なのは、このようなアニメ表現の可能性を試す、自由なフィールドのように思う。そして、その挑戦をいかにビジネスの中に着地させていくか。
この複雑に絡みあった問題こそ、今のアニメの解くべき問題のはずだ。その問題も露わにした作品だった。
文:藤津亮太(アニメ評論家/@fujitsuryota)
掲載:2012年6月20日
⇒『虹色ほたる~永遠の夏休み~』映画公式サイト
⇒blog 藤津亮太の「只今徐行運転中」
⇒【amazon】『チャンネルはいつもアニメ―ゼロ年代アニメ時評』(著:藤津亮太)
⇒『おおかみこどもの雨と雪』「おおかみこども」と「母」と「花」/帰ってきたアニメの門 第8回
⇒『グスコーブドリの伝記』ブドリの妹捜しがこんなに幻想的なわけ/帰ってきたアニメの門 第7回
⇒『LUPIN the Third ‐峰不二子という女‐』vs「ルパン」/帰ってきたアニメの門 第5回
⇒『銀魂』コンテンツじゃない、番組だ。/帰ってきたアニメの門 第4回
⇒『ちはやふる』スポーツアニメの面白さ/帰ってきたアニメの門 第3回
⇒『男子高校生の日常』とキャラクター/帰ってきたアニメの門 第2回
⇒帰ってきた『日常』/帰ってきたアニメの門 第1回
⇒特集:アニメのゆくえ2011→「2011年もチャンネルはいつもアニメですか?」藤津亮太インタビュー
⇒テレビアニメを見ながら『あにらび!』で実況tweet!