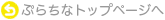[第8回]『おおかみこどもの雨と雪』「おおかみこども」と「母」と「花」
子供のころ、両親のなれそめに興味を持って尋ねたことのある人は多いだろう。そこで語られる「やがて2人が結婚することを前提とした思い出語り」は、子供にとって、お姫様と王子様が出会い、「めでたしめでたし」で締めくくられるおとぎ話に限りなく近い。
「おとぎ話みたいだって、笑われるかもしれません。/そんな不思議なことあるわけないって。/でもこれは確かに私の母の物語です」
このようなナレーションで開幕する『おおかみこどもの雨と雪』は、確かにおとぎ話のような映画だった。
天涯孤独な女子学生・花が、偶然<彼>と知り合い、おおかみおとこであるという<彼>の秘密を知ってなお受け入れ、結ばれる。
親への言及が少なく、バックグラウンドをあえて詳細には描かれていない花と<彼>は、まるでおとぎ話の登場人物のようだし、さら成長した二人の娘・雪による回想形式のナレーションであることも加わって、この序盤の展開からは「お姫様と王子様」のおとぎ話が思い浮かぶ。
出会うべきパートナーと出会うことで終わる「おとぎ話」。もちろんこの映画はそこで「めでたしめでたし」と終わるわけではない。むしろ、<彼>が不慮の事故で死に、雨と雪という姉弟を抱えた花が2人を育て上げる様子こそがこの映画の本題といえる。そして、本作はそこからもまた「おとぎ話」であろうとする。そこにこの映画の一番の特徴がある。
子育てというのは「巣立つことを期待しながら、慈しみ続けようとする」という矛盾を孕んだ行為だ。だからこそ、巣立ちはいつも、慈しむ親にとって一種の裏切りとして起こる。これは劇的ではあるが、しかし同時に親という存在に最初から織り込まれた「想定の範囲内」の出来事でもある。
この「想定の範囲内にある巣立ち」を前提に、そこへと向かう経路としてさまざまな思い出が語られていくと、そこには両親のなれそめを聞くのに似た「おとぎ話」らしさが立ち上がってくる。
序盤がベターハーフと出会う「少女のおとぎ話」とするのなら、この映画の中盤以降で語られるのは「母のおとぎ話」と呼べるだろう。「少女のおとぎ話」が愛の成就を目指して進行するように、「母のおとぎ話」は「子供の巣立ち」という「めでたしめでたし」に向けて進行していくのだ。
本作は、この二つの「おとぎ話」を、それにふさわしいシンプルで力強い演出で語っていく。
語り手が生まれる前の「少女のおとぎ話」はロングショットが多く、それがナレーターの雪が語る“現在”からの距離を感じさせる。<彼>が自分がおおかみおとこであることを告白する時、運命の変転を予感させるように、星空の星が速い速度で回転する。「母のおとぎ話」になってからは、小学校に入ってからの2年を、廊下から見た教室をPANしてくだけで表現したかと思えば、檻の中のシンリンオオカミの寂しげにも恐ろしくも見える姿をFixでとらえる。
このような引き締まったカットを無駄なく積み重ねることで十数年にわたる時間が、約2時間の中に過不足なく織り込まれていく。この語り口は見事だ。
ただし忘れていけないのは「母のおとぎ話」を語るために、意図的に“編集”され、フレームの外へと置かれたものもある。それは「社会と花の関わり」であり「花自身の人生」だ。
たとえば花は、予防接種を受けさせていないことなどから、ネグレクトを疑って児童相談所の児童福祉司がやってきても玄関から閉め出してしまう。そのほか数年にわたって<彼>の残した「わずかの貯金だけで暮らしている」という展開や、「廃屋同然だった古民家を花一人で修理してしまったであろう描写」。さらには仕事を決めるときも「高校生のアルバイトのほうがよっぽど時給がいい」と言われながらも、自然観察員の補佐の仕事を選ぶ。
映画の中でこれらの問題が、どのように解決したかを具体的に描かれることはない。花や<彼>の生い立ちを詳細に語らないことと同様、問題解決するために社会と花の間に起きたであろう対峙もフレーム外の出来事として処理されることで、映画は「おとぎ話」と呼びうるシンプルな構成を保つことができている。
そして世間と交流はしても社会として対峙することのない花は、母として「おとぎ話」を生きている。だから彼女個人がどのような人生を生きたいと願っているかについてもまた、フレームの外に出てしまってなかなか見えてこない。
映画のラストで、二人の子供が巣立っていった後、彼女は<彼>の写真とほほえみ合うだけでなにもしていないのは象徴的だ。そこにあるのは「母の余生」であって、花の人生ではない。「母のおとぎ話」は、花の人生をフレームの外へ押し出してしまっているのだ。
本作の物語が、雪と雨の側から読みとった時と、花の側から読みとった時とで印象が大きく異なるのは、この「母としての花」と「個人としての花」のバランスが大きく偏っているところに理由がある。それによって「めでたしめでたし」と「おとぎ話」を終えられるか、それとも「めでたしめでたし」の後に続く現実を考えてしまうか、物語の受け取り方にも違いが出てくる。
<彼>は「同じ団地でも家の中はまるで違うんだ」と語った。それはつまり「普遍的な家庭像」などなく、人は自分が暮らした家族のことしか知らないということでもある。花が映し出すのは、そういった各人の家族観でもあるはずだ。
文:藤津亮太(アニメ評論家/@fujitsuryota)
掲載:2012年8月17日
⇒『おおかみこどもの雨と雪』映画公式サイト
⇒blog 藤津亮太の「只今徐行運転中」
⇒【amazon】『チャンネルはいつもアニメ―ゼロ年代アニメ時評』(著:藤津亮太)
⇒『グスコーブドリの伝記』ブドリの妹捜しがこんなに幻想的なわけ/帰ってきたアニメの門 第7回
⇒『虹色ほたる~永遠の夏休み~』アニメーションの輝きが照らす問題/帰ってきたアニメの門 第6回
⇒『LUPIN the Third ‐峰不二子という女‐』vs「ルパン」/帰ってきたアニメの門 第5回
⇒『銀魂』コンテンツじゃない、番組だ。/帰ってきたアニメの門 第4回
⇒『ちはやふる』スポーツアニメの面白さ/帰ってきたアニメの門 第3回
⇒『男子高校生の日常』とキャラクター/帰ってきたアニメの門 第2回
⇒帰ってきた『日常』/帰ってきたアニメの門 第1回
⇒特集:アニメのゆくえ2011→「2011年もチャンネルはいつもアニメですか?」藤津亮太インタビュー
⇒テレビアニメを見ながら『あにらび!』で実況tweet!